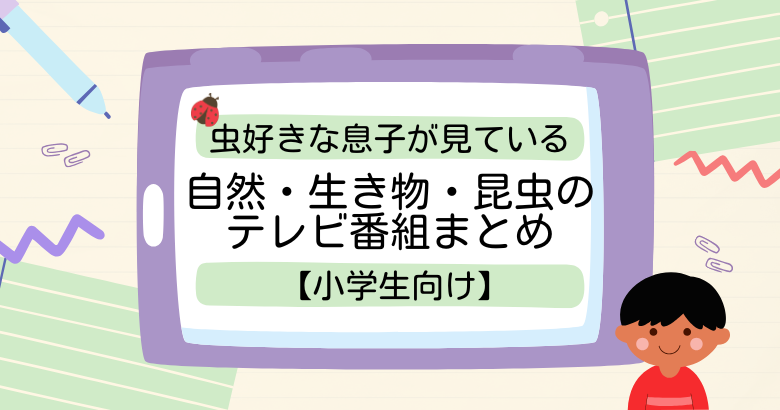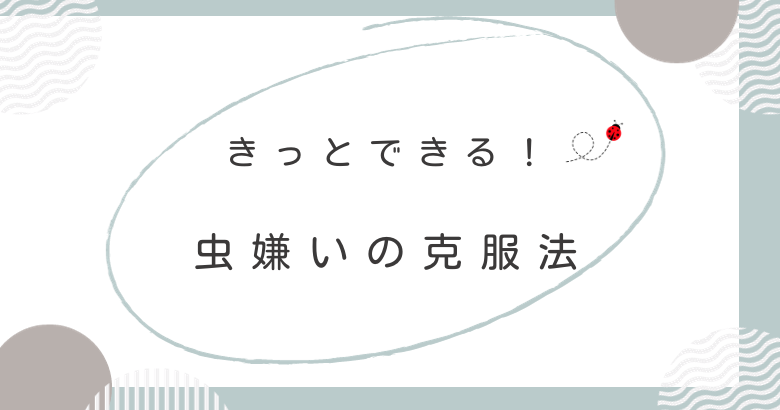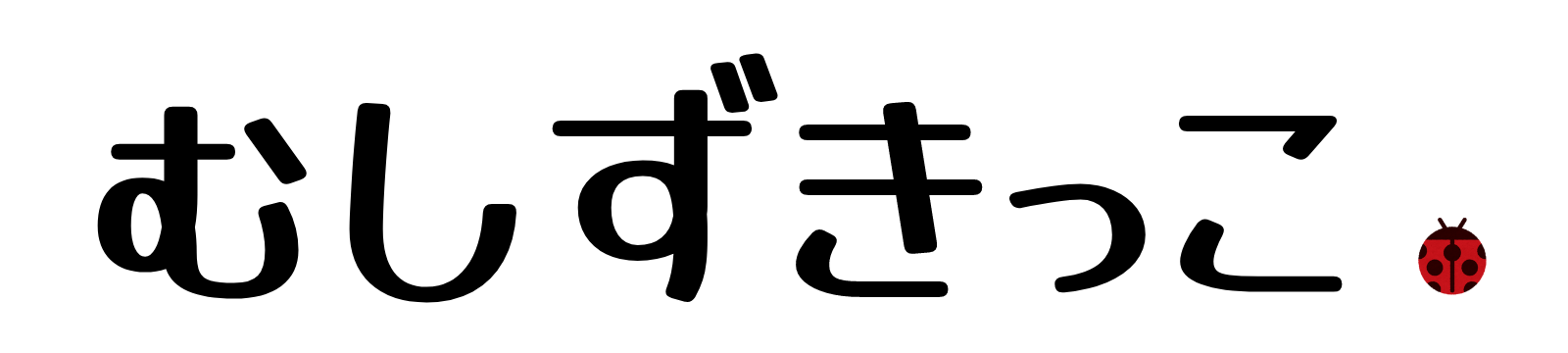息子が虫好きになってから5年間、さまざまな虫かごや飼育ケースを使ってきました。
虫とりをしてこなかった私(母)は、最初は虫かごと飼育ケースの違いについてよくもわからず、虫かごは「とりあえず虫が入って持ち運べればいいでしょ」くらいの感覚で選んでいました。
いろいろ使ってきた中で、「この虫かごはこんな虫をとる時に向いているな」とか「この飼育ケースはこんな悩みを解消してくれるな」など、用途によって使い分けると便利なものだということを知りました。
今回は、幼児~小学生の虫好きの子どもにオススメの虫かごと飼育ケースについて、小1の息子が愛用しているものを中心に紹介したいと思います。
- 幼児~小学生でも使いやすい虫かご・飼育ケースのオススメを知りたい
- 虫を飼うときに使う飼育ケースの選び方を知りたい
- 室内で飼いたい!コバエ対策ができる飼育ケースはある?
という方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
虫とり網について紹介している記事はこちら

虫かごと飼育ケースはどう違う?
虫かごと飼育ケースはよく似ていますが、以下ように用途や構造が少し違います。
昆虫採集や一時的な飼育に向いている
- 軽くて持ち運びしやすく、ひもがついている商品が多い
- メッシュやスリットになっていて通気性が良い
- 子どもが外で捕まえた虫を一時的に入れて観察するのに便利
長期間の飼育・繁殖・観察に向いている
- しっかりした作りで、フタが外れにくい
- 底が深く、土や木などのレイアウトができる
- 通気口がありつつもほどよい湿度が保てる構造
このように、虫とり(外遊び)→虫かご、長期で飼育→飼育ケース、という認識で基本的にはよいかと思います。
ただ、虫とりについては、ダンゴムシなどの土の中の生き物をとる目的であれば土や落ち葉を入れられる小さな飼育ケースの方が向いていますし、そのまま飼うこともできるので楽です。
虫とりに行く場合は、目的や使うシーンによって「虫かご」と「飼育ケース」を使いわけるのがいいですね。
 むしはは
むしはは虫が好きになったばかりで、虫とり網を使わないダンゴムシやバッタとりがメインの頃なら、小さな飼育ケースが便利です。虫とり網で蝶などをとるようになったら、虫かごもそろえるといいかと思います。
厳選!幼児~小学生にオススメの虫かご



虫が大好きな息子が愛用している虫かごを2つ紹介します
セリアの飼育ケース
息子は虫とりに夢中になればなるほど、虫かごの扱いがどうしても雑になります。
なので、なるべく丈夫な虫かごを選ぶようにしていますが、できれば値段も安いとうれしい。
そんなわが家のワガママに応えてくれる商品が、なんと100均セリアにありました。


こちらは飼育ケースとして販売されているんですが、小さくて軽く、持ち手も付いていて持ち運びしやすいため、わが家では虫とりに持って行くことが多いです。
100均の虫かごと飼育ケースはいろいろと使いましたが、中でもこのセリアの飼育ケースはかなり優秀でした。
110円という圧倒的な安さにもかかわらず、丈夫に作られた日本製の飼育ケースで、コスパはバツグン。
すぐ物を壊してしまう、幼児~低学年の小さな子どもが使う虫かごにピッタリです。
飼育ケースなので、土や落ち葉も入れられますし、そのまま飼えるところも気に入っています。
ただ、飼育ケースを虫かごとして使うデメリットとして、肩掛けはできない点、夏場にはケース内が高温になり蒸れてしまい、虫が弱りやすくなる点に注意が必要です。



セリアの飼育ケースは、息子のお友達も虫かごとして使っている子が多いです
- 虫かごとしても使える
- 日本製でしっかりとした作り
- 110円という圧倒的な安さ
- 土や落ち葉をいれることができる
- 飼育ケースのため、肩掛けはできない
- 夏場に虫かごとして使用すると、虫が弱りやすい
虫かご「アイケージ」(池田工業社)
2点目に紹介するのは、虫かご・飼育ケースの定番ブランドである池田工業社から販売されている虫かご「アイケージ」です。


虫かご「アイケージ」は、側面が金網になっているのが特徴で、上部には細かいスリットが入っています。
この虫かごの一番のお気に入りポイントは、中に入れた虫が弱りにくいところです。
先ほど紹介したセリアの飼育ケースの場合、夏場に虫かごとして使用すると、ケース内が高温になり蒸れるため、虫が弱りやすくなるところが難点でした。
一方、虫かご「アイケージ」はメッシュ構造で通気性がよく、夏場でも虫にとって比較的快適な環境を維持しやすいです。
また、昆虫の足が引っかかりにくく、ツルツルと滑ってしまう素材や構造の虫かごも多いですが、虫かご「アイケージ」は金網の目に昆虫の足がひっかかりやすいため、中で過ごす虫にとって負担が少なそうに感じます。
さらに、目が細かいことで、幅広いサイズの虫を入れることができる点も気に入っています。
例えば、春に出てきたばかりのバッタやカマキリの幼虫などの小さなサイズの虫をつかまえても、隙間から逃げられることがありません。



気づかないうちに隙間から脱走されること、よくありますよね
虫かご「アイケージ」のふたは力の弱い幼児が開けやすいスライド式で、調節可能な肩掛けベルト付きです。
価格は1000円台(2025年11月現在)で決してリーズナブルな虫かごとは言えないかもしれませんが、丈夫で使いやすい点、夏場の虫とりでも虫かご内の虫が弱りにくい点、幅広いサイズの虫を入れることができる点から、個人的には十分満足できる価格と思っています。



息子は4歳の頃から3年以上使っていますが、割れたり欠けたりもなく丈夫でまだまだ使えそうです。
見た目重視のキャラクターものから昔ながらのものまで、虫かごはいろいろ持っていましたが、息子は「アイケージ」を選んで持って行く率が圧倒的に高く、それにも関わらず壊れることがないところが「すごいな」と感じています。
- 虫にとって比較的快適な環境を維持しやすい構造
- 小さなサイズの虫(バッタやカマキリの幼虫など)が隙間から逃げない細かな目
- 力の弱い幼児が開けやすいスライド式のふた
- 調節可能なベルト付きで肩掛け可能
- 丈夫に作られている
- 砂や水は入れることができない
- 1000円台で虫かごの中では高価な部類
蝶の羽を傷つけにくいやわらかいメッシュタイプも便利です。
子どもが昆虫を飼うときの飼育ケースの選び方
飼育ケースは、飼う虫の種類と目的(観察・繁殖・飼育期間)に合わせて選びます。
さまざまな素材のケースがありますが、子どもが触るものなので、割れにくい素材、特にプラスチック製のものがオススメです。
軽くて開閉しやすいものを選ぶとお世話のストレスが少ないです。
昆虫別!飼育ケースの目安サイズとポイント
飼育ケースは飼育する生き物に合わせてサイズを選びます。
| 飼う生き物 | 目安サイズ | ポイント |
|---|---|---|
| カブトムシ・クワガタ(成虫) | 中〜大(20〜30cm幅) | 転倒防止のための木や枝も入れるため広さのある飼育ケースがよい。特にカブトムシは脱走対策が必要。 |
| カブトムシ・クワガタ(幼虫) | 中〜大(深めタイプ) | 土を10cm以上入れられる深型がよい。通気より保湿重視。コバエ対策がされているケースがオススメ。 |
| コオロギ・バッタなど跳ねる虫 | 中サイズ+フタがしっかり閉まるタイプ | 飛び出して逃げないよう、ふたがしっかりしまるケースがオススメ。通気性重視。 |
| カマキリ・クモなど肉食性 | 小〜中 | 捕食の様子を観察するなら透明度重視。掃除しやすい構造がよい。 |
| ダンゴムシ・カタツムリなど | 小〜中 | 通気と湿度のバランスが大事。 |



虫によってベストなサイズの飼育ケースがあるんですね
蝶の羽が傷つきにくいネット状の飼育ケースもオススメです
ネット状の飼育ケースは羽化を観察するときに使っています


いろんな生き物の飼育方法についてくわしく知りたい方は、こちらの図鑑がオススメです
昆虫マットを入れる場合にオススメの飼育ケース
通常の飼育ケースはふたに通気口があり、外の空気が入るような構造になっていますよね。
この通気口が大きいと、通気性がよくなりますが、昆虫マットが乾きやすくなったり、外からコバエが侵入してマットなどに卵を産んで繁殖してしまうトラブルが発生しやすくなります。
逆に、通気口が小さいと、通気性は悪くなりますが、昆虫マットが乾きにくくなり、外からのコバエの侵入を防ぐことができます。
つまり、通気口が小さい飼育ケースは、昆虫マットを入れる場合には向いている環境といえます。
ここからは、通常の飼育ケースに比べて通気口が小さい飼育ケースを2種紹介したいと思います。
- できるだけ昆虫マットの霧吹き作業を減らしたい
- コバエを繁殖させないようにしたい
という方は参考にしてみてくださいね。
スライダー式飼育ケース
通常の飼育ケースとは違い、スライダー式飼育ケースはふたを左右にスライドして開閉します。
一部だけ開けられる構造のため、昆虫が逃げにくく、作業がしやすいのが特徴です。
また、ふた全体が透明なので、外さなくても中の様子が観察しやすいです。



スライダー式飼育ケースは、力の弱い幼児でも簡単に開け閉めできます
そして、ふたの部分には通気口がついていますが、通常の飼育ケースに比べると小さめのことが多いです。
コバエがケース内に侵入しにくく、昆虫マットの湿度を一定に保ちやすいことから、「カブトムシやクワガタ飼育に向いている」と紹介されている商品が多いです。
このように、スライダー式飼育ケースは、やや通気性が悪いという特徴がありますが、わが家ではあまり気にせず何でも気軽にスライダー式飼育ケースに入れて飼ってしまっています。
通常の飼育ケースに比べると若干割高ではありますが、ダイソーにも売っており、330円という安価(2025年11月現在)でスライダー式飼育ケースを手に入れることもできます。



ダイソーのスライダー式飼育ケースは小さい子どもの昆虫観察や飼育にピッタリで、息子も愛用しています
スライダー式飼育ケースには、ふた部分にスライドさせるのに必要な溝がありますが、この溝に昆虫マットなどが詰まりやすいです。
この溝部分が詰まると開閉がスムーズにいかなくなりますので、通常の飼育ケースに比べると少し掃除が面倒かもしれません。
- ふたを横にスライドして開閉
- 開けやすい/観察しやすい/湿度保持/コバエ侵入防止(メリット)
- 通気性やや低め/蓋の溝の掃除が必要/やや高価(デメリット)
- マットの湿度を保つ必要がある昆虫の飼育の方が向いている
ラージサイズ
コバエ対策に特化した飼育ケース
先に紹介したスライダー式飼育ケースも通常の飼育ケースに比べるとコバエが入りにくい構造ですが、さらにコバエの侵入防止に特化した商品も販売されています。
特に、室内で飼う場合はコバエ対策を何より重視したい方も多いのではないでしょうか?



わが家は室内で飼っているので、昆虫ゼリーや昆虫マットに寄ってくるコバエには悩まされていました
まず、外からのコバエ侵入を阻止するためには、以下の2点が大切です。
- コバエ対策用の通気口が小さい飼育ケースを使う
- ノーマル仕様の飼育ケースにコバエ侵入防止シート(小さな通気穴が開いているシート)をセットする
①も②も単に「極力隙間が少ない構造にして、外からのコバエの侵入を防ぐ」というものです。



スライダー式飼育ケースよりもっと隙間が少なくなります
スライダー式飼育ケースよりもっと通気性は悪くなるので、カビやケース内の温度にも注意しなくてはいけません。
しかし、コバエ対策と昆虫マットを使った飼育は相性がいいと言えます。
それから、コバエ対策を考える上で忘れてはいけないのが、「飼育ケースやシートだけでは完全に防げない」ということです。
飼育ケースやシートは外からのコバエの侵入対策にはかなり有効ですが、購入した朽ち木や昆虫マットにすでにハエの卵が産み付けられていた場合、それらをケースに入れると内部で繁殖します。
しかしながら、もしそうなったとしても隙間の少ない構造になっていれば、部屋に飛び出していくこともありませんよね。
先の①や②の方法で対策することで、家の中をハエが飛び回ったり、昆虫マットに卵を産み付けられて繁殖するリスクがぐんと減ることは確かですから、室内で飼育するハードルは低くなります。



昆虫マットの中には、抗菌・カビ抑制仕様やコバエ防止仕様のものも販売されていますので、お悩みに合った商品をうまく組み合わせるといいかもしれません
- 外からのコバエの侵入を防止する飼育ケース
- コバエ侵入防止/湿度保持(メリット)
- やや高価/換気・温度管理に注意が必要(デメリット)
- マットの湿度を保つ必要がある昆虫の飼育に向いている
- 外からの侵入以外が原因のコバエについては別途対策が必要
通常の飼育ケースでできるコバエ侵入防止策
各種お悩み対策用マット
まとめ
今回は、息子が愛用している虫かごや飼育ケースを中心にオススメを紹介しました。
今までたくさんの虫かごや飼育ケースを使いましたが、すぐ壊れてしまったり、使いにくかったり、私には理由がわからないけれど息子はなぜか使いたがらない、みたいなものもありました。
サイズやデザイン、使用目的別にいろいろな虫かごや飼育ケースがあり、おもしろいですよね。
虫かごや飼育ケースをうまく使い分けて、少しでも快適な虫ライフを過ごしてみてはいかがでしょうか。