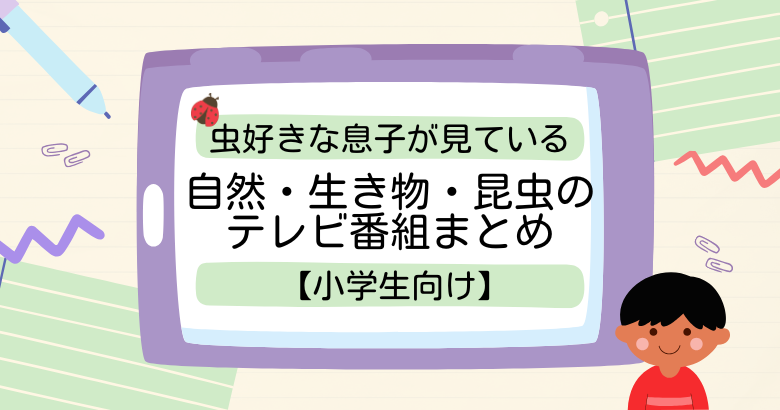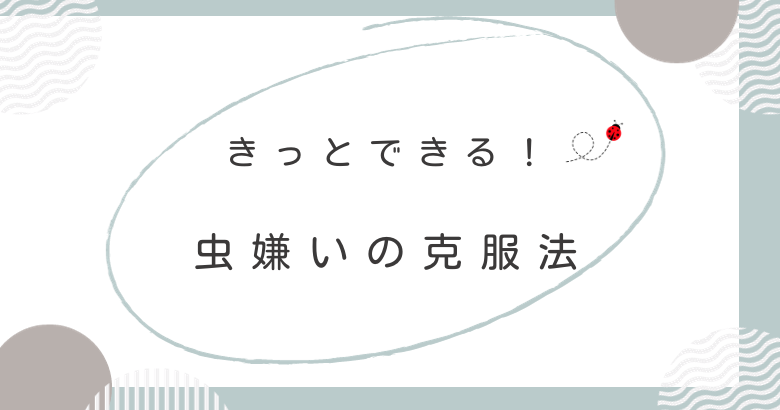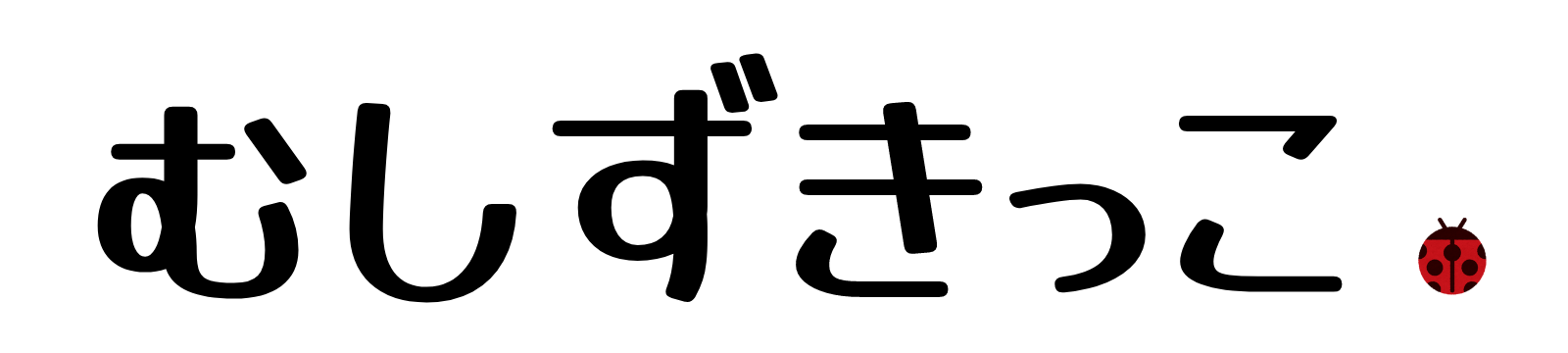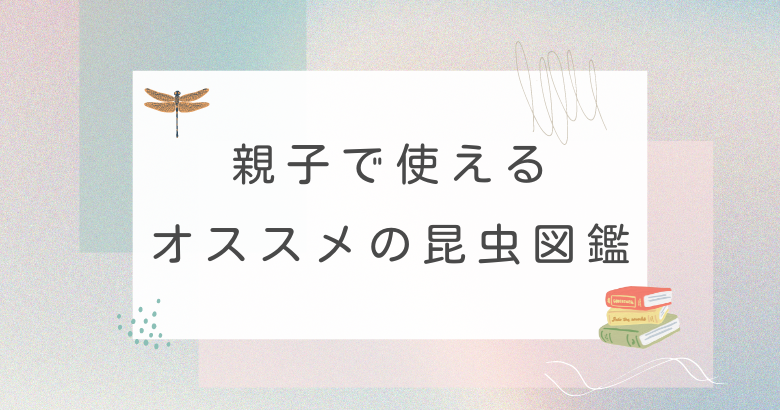もうすぐ6歳になる息子は、虫が大好きです。
虫をつかまえては、親子で図鑑を開き、「何ていう名前の虫なんだろう?」と話しながら、たくさん調べてきました。
息子は図鑑をながめることも好きだったので、わが家にはいつの間にか虫に関する図鑑が集まっていました。
今回は、虫好きの子どもが喜ぶ図鑑を知りたい方に向けて、息子が実際に読んでいる昆虫図鑑をレビューとともに紹介します。
それぞれの昆虫図鑑の特徴と違いもまとめましたので、図鑑選びに迷っている方は最後まで読んでみてくださいね。
図鑑の定義
当記事で紹介する図鑑とは、
鳥・魚・こん虫などを、図や写真で具体的にわかりやすく説明した本
金田一京助編『国語辞典』第十一版、小学館、2019年、p.649「図かん」
とします。
タイトルが「図鑑」となっていても、内容が物語であれば「絵本」に分類することとします。
図鑑は購入すべき?

結論から言うと、図鑑は購入するのがオススメです。
図書館でも図鑑は借りて読むことができます。
しかし、経験上「あとで調べよう」と思って後回しにすると、大抵調べないんですよね。
「知りたい」と思ったその時に調べないと、あとで思い出しても「まぁいいか」とめんどうに思って、結局調べなかったりするものです。
スケジュールを確認して図書館へ足を運び、重い図鑑を借りて家に持ち帰り、そのあと過去につかまえた昆虫を調べる・・・というのは、忙しい親にとってかなりハードルの高いことだと思います。
 むしはは
むしはは調べものがある度に図書館に行って、重い図鑑を借りたり返したりするのは、あまり現実的ではないですよね
なので、子どもが虫に興味があれば、昆虫図鑑を購入するのがオススメです。
たくさん買わなくても、まずは日本の昆虫が載っている定番の図鑑が一冊あればOKです。
知りたい時にすぐに調べられる環境を作ることが望ましいのかなと思います。
また、「インターネットがあれば、図鑑は必要ないのでは?」という方もいらっしゃるでしょう。
そうですよね。「虫を特定する」という目的であれば、インターネットで十分です。
では、インターネットにはない、図鑑のいいところは何でしょう?
- 幼児でも練習すれば自分で調べることができる
- 偶然開いたページで「こんな虫もいるんだ!」という新たな発見がある
- 虫が好きなら何度も読むことになるので、高価なようで実はコスパがよい
- 読解力が育つ1
特に、字が読めるようになれば、「自分で調べることができる、読める」ところが、図鑑の一番いいところだと思っています。
昆虫図鑑が一冊家にあるだけで、かなり虫にくわしくなりますよ。
ちなみに、知らない虫がいて調べたい時、私はインターネットも利用しています。
外来種の昆虫は図鑑に載っていないことが多く、そんな時はインターネットで調べると特定できるからです。
図鑑もインターネットもそれぞれいいところがあります。
うまく利用して、虫にくわしくなりましょう。
定番の日本の昆虫図鑑
小学館の図鑑NEO〔新版〕昆虫
昆虫図鑑の定番中の定番ではないでしょうか。
シンプルで調べやすく、わが家ではもっとも使われている図鑑です。
幼虫、蝉の抜け殻、雄雌、卵・蛹などの写真も一部掲載されています。
興味深いコラムが多く、本としても読んでもおもしろいです。
80分の見応えたっぷりのDVDには、ドラえもんが登場します。
DVDの内容はおもしろく、映像がとてもきれいです。
息子は数え切れないほど、繰り返し見ていますが、大人が見てもおもしろいですよ。



はじめての昆虫図鑑にオススメです!
- 日本で見られる昆虫約1400種掲載
- 分類(目)ごとに掲載
- 1匹ごとに簡単な解説と、分類(科)・大きさ・分布・成虫が見られる時期、食べ物、鳴き声などの情報
- 大きいサイズ
- 80分のDVD付き(ドラえもん登場)
- 昆虫用語集がある
- ふりがなあり
小学館の図鑑NEO POCKET 昆虫
持ち運びに便利な『小学館の図鑑NEO』の小さいサイズの昆虫図鑑です。
大きい方の『小学館の図鑑NEO』同様、こちらもシンプルで使いやすく、野外で昆虫を観察するときに役立つコラムなんかも載っています。
『小学館の図鑑NEO』の大きいサイズには付いているDVDは、こちらには付いていません。
小さいサイズなので掲載されている昆虫数も少なめですが、その分価格も抑えられています。
虫とりに持って行けるシンプルな図鑑を探している方、そこまでくわしい内容を求めていない方に特にオススメです。
- 日本で見られる昆虫約850種掲載
- 分類(目)ごとに掲載
- 1匹ごとに簡単な解説と、分類(科)・大きさ・分布・成虫が見られる時期、食べ物、鳴き声などの情報
- 持ち運びできる小さいサイズ
- 昆虫用語集がある
- ふりがなあり
講談社の動く図鑑 MOVE mini 昆虫
『講談社の動く図鑑MOVE』の小さいサイズ、『MOVE mini』シリーズの昆虫図鑑です。
こちらの図鑑は小さいサイズでありながら、約1100種の昆虫が掲載されています。
掲載数が多くても写真が小さく見にくいということはなく、好奇心が刺激されるような写真がダイナミックに使われている印象です。
こちらの図鑑は、「絶滅危惧種」や「珍しい」の情報も載っており、つかまえた昆虫を調べるときに参考になります。
そして、スマホやタブレットで見ることができるデジタル図鑑(電子書籍のようなもの)がおまけでついてくるところもポイントです。
明るいデザインの図鑑を探している方、掲載数が多いコンパクトな図鑑を探している方に特にオススメです。



『MOVE mini』のデジタル図鑑は以下の記事で紹介しています
- 日本で見られる昆虫約1100種掲載
- 分類(目)ごとに掲載
- 1匹ごとに簡単な解説と、分類(科)・体長・分布・住んでいる環境・成虫が見られる時期、食べ物、鳴き声などの情報
- 「絶滅危惧種」「珍しい」の記載あり
- 持ち運びできる小さいサイズ
- デジタル図鑑がおまけでついてくる
- ふりがなあり
『小学館の図鑑NEO POCKET 昆虫』『講談社の動く図鑑MOVE mini 昆虫』をくらべてみた!
『小学館の図鑑NEO POCKET 昆虫』『講談社の動く図鑑MOVE mini 昆虫』は、どちらも日本の昆虫を調べることができる、小さいサイズの昆虫図鑑です。
実際に使ってみた感想は、どちらの方が優れているというわけではないということです。



正直なところ、好みの問題かと思います
ちなみに、わが家は『ネオぽけっと(小学館)』を虫とりに持って行く目的で購入したあと、『ムーブミニ(講談社)』を購入しています。
『ネオぽけっと(小学館)』の内容に不満があったわけではなく、単純に『ムーブミニ(講談社)』もおもしろそうだから読みたいという理由で購入しました。
図鑑の使いやすさについては好みが分かれると思いますので、中を確認した上で購入するのがオススメです。
ネット通販の試し読み(書籍によってある場合とない場合がある)、図書館、大型書店に置いてある見本で中は確認できますよ。
2冊を比較してまとめましたので、参考にしてみてくださいね。
- 掲載種:ムーブミニの方が多い(ネオぽけっと:約850、ムーブミニ:約1100)
- 1匹ごとの情報:基本情報に加え、ムーブミニは「絶滅危惧種」「珍しい」の記載あり
- 本の大きさ:ネオぽけっとの方が若干小さい
- 本の厚み:同じ
- ふりがな:ともにあり
- デザイン:ネオぽけっとはシンプル、ムーブミニはカラフル
- ネオポケットは「完全変態」などの用語解説のページあり
- 幼虫やセミの抜けがらなど、成虫以外の姿の写真はネオポケットの方が多い
- ムーブミニはデジタル図鑑がついてくる
- 主観ですが、ネオぽけっとは調べやすさを重視して作られている印象、ムーブミニは子供の好奇心や楽しい気持ちを重視して作られている印象
学研の図鑑LIVE POCKET Special 沖縄の昆虫
『学研の図鑑LIVE』の小さいシリーズ『学研の図鑑LIVE POCKET』シリーズの昆虫図鑑で、鹿児島県南部から沖縄県で見られる昆虫を調べることができます。
こちらの図鑑はシンプルなデザインで、識別方法やコラムなども載っています。
同じ日本でも、地域によって見られる昆虫って違うんですよね。
こちらの図鑑は石垣島旅行に持って行ったんですが、石垣島の昆虫は普通の昆虫図鑑には載っていない昆虫ばかりだったので、とても役立ちました。
ページにあるQRコードを読み込むと、鳴き声や動く様子の動画をスマホで再生でき、より深く昆虫を知ることができますよ。
色あざやかな南国の昆虫がたくさん載っている、オススメの図鑑です。
- 鹿児島県南部から沖縄県で見られる昆虫約600種掲載
- 分類(目・科)ごとに掲載
- 1匹ごとに簡単な解説と、大きさ・成虫が見られる時期・成虫が見られる環境、分布などの情報
- 持ち運びできる小さいサイズ
- 用語解説集あり
- ページのQRコードを読み取ると、動画をスマホで再生できる(鳴き声、動く様子など)
- 簡単な漢字にはふりがななし
定番の世界の昆虫図鑑
角川の集める図鑑 GET!昆虫
『角川の集める図鑑GET!昆虫』は大きいサイズの図鑑で、世界中の昆虫を調べることができます。
こちらの図鑑を購入した一番の理由は、昆虫が地域別で掲載されているからです。
「ニジイロクワガタ」の生息地「オーストラリア」がどこにあるかまでチェックできれば、好きな昆虫と絡めて地理の学習ができますよね。
世界地図や地理にも興味を持ってほしくて、ずっとこのような本や図鑑を探していたんですが、やっと見つけたのがこちらの図鑑でした。
『GET!図鑑』は、世界地図全体と東南アジアなどのエリアごとに地図が載っており、地図上には、生息している昆虫の絵が描かれており、目的にぴったりだったので購入を決めました。
さらに、オンラインサービス「GET!+」を利用すると、カードをコレクションして自分の図鑑をつくって遊べます。
地域別になっている昆虫図鑑、子ども受けしそうな図鑑を探している方にオススメです。
- 世界の昆虫約1500種掲載
- 地域ごと・環境ごとに分けて掲載
- 1匹ごとに簡単な解説、分布・幼虫の食べ物などの情報
- 世界地図上に昆虫が描かれている
- オンラインサービス「GET!+」で遊びながら学べる
- 大きいサイズ
- 用語解説集あり
- ふりがなあり
小学館の図鑑NEO 昆虫2 地球編
『小学館の図鑑NEO』シリーズの『昆虫2』は世界の昆虫図鑑です。
こちらは日本の昆虫図鑑である『昆虫1』とは全然違い、コラムや説明がほとんどありません。
博物館で飾ってある標本がそのまま本になったような、写真メインの図鑑です。
昆虫の名前もアルファベット表記になっているものが多いので、幼児には写真を見て楽しむ使い方になるのかな、と思います。
こちらも『昆虫1』と同様、ドラえもんが登場する70分の見応えたっぷりのDVDが付いています。
世界の昆虫の美しい映像やおもしろい映像を見ることができます。
博物館でしか見ることができない貴重な昆虫を家でも眺めることができる、オススメの図鑑です。
- 世界の昆虫2000種以上掲載
- 分類(目)ごとに掲載
- 1匹ごとに採集地などの情報
- 大きいサイズ
- 70分のDVD付き(ドラえもん登場)
- ふりがなあり(ただし、アルファベット表記多数)
「角川の集める図鑑 GET!昆虫」「小学館の図鑑NEO 昆虫2地球編」をくらべてみた!
『角川の集める図鑑GET!昆虫』『小学館の図鑑NEO昆虫2地球編』は、どちらも世界の昆虫が載っている大型の図鑑です。
実際に使ってみて、『GET!昆虫(角川)』は子どもが興味を持ちそうなところから世界の昆虫について学べる図鑑、『昆虫2(小学館)』は視覚から世界の昆虫に興味を持てる図鑑といったように、アプローチ方法が全然違うと感じました。
ただ、『昆虫2(小学館)』の付属のDVDは、世界の昆虫について楽しく学べる内容になっており、図鑑とDVDでバランスがとれていると思います。
2つの図鑑について以下にまとめましたので、参考にしてみてくださいね。
- 掲載種:『昆虫2』の方が多い(GET!昆虫:約1500、昆虫2:約2000)
- 1匹ごとの情報:『GET!昆虫』の方が多い
- 本の大きさ:ほぼ同じ
- 本の厚み:ほぼ同じ
- ふりがな:ともにあり
- 昆虫の分け方:『GET!昆虫』は地域ごと、『昆虫2』は分類ごと
- 『昆虫2』は英名はアルファベット表記多数(『GET!昆虫』はアルファベット表記なし)
- デザイン:『GET!昆虫』は楽しい雰囲気、『昆虫2』はシンプル
- 『GET!昆虫』は遊びながら学べるオンラインサービス(GET!+)がある
- 『GET!昆虫』は、楽しさを重視して作られている印象、『昆虫2』はビジュアルを重視して作られている印象(DVDはおもしろい、楽しい映像)
興味を持ち始めたばかりの幼児向け昆虫図鑑
こどものずかんMio むし
絵本と図鑑の中間のような本です。
たとえば、「キャベツ畑のモンシロチョウのくらし」や「草むらでどんな虫が見つかるか」など、身近な虫への興味を引き出すような内容が中心で、小さな子どもにもわかりやすく虫が紹介されています。
トンボやカマキリなどの定番の虫の図鑑からクイズまで、バラエティーに富んでいて飽きません。
出版社「ひかりのくに」のHPによると、こちらの図鑑の対象年齢は5・6歳~となっていますが、3・4歳くらいから理解できるやさしい言葉で書かれています。
写真とイラストがたくさん使われており、虫に興味がない子どもでも楽しく読むことができます。
本格的な図鑑はまだ必要ないけれど、自然への興味を持つきっかけに昆虫図鑑を探している方には、ぴったりの図鑑です。
- 日本の昆虫
- 幼児向け(5~6歳くらいから)
- 絵本と図鑑の間のような内容
- 絵本サイズ
- ふりがなあり
- クイズあり
- 写真やイラストが豊富
- 虫や自然に興味を持ったばかりの子供が楽しめる
小学館の図鑑NEO まどあけずかん むし
『まどあけずかん むし』は、楽しみながら読むことで虫について学べる図鑑です。
厚紙のページにはたくさん窓が付いており、窓をめくると虫の情報が出てきます。
中身が見たくなる心理を利用して、窓を開けていけばいくほど虫にくわしくなる、子どもがハマるおもしろい図鑑です。
個人的に一番気に入っているところは、大好きな虫を通して英語も学べるところです。
ニイニイゼミやハラビロカマキリなど、昆虫好きにはおなじみの虫でも、英語でなんて言うのかまでは知らなかったりします。
実際、息子に「この虫は英語でなんて言うの?」とよく聞かれるんですが、かなり多くの昆虫の英語名が載っているので便利です。
大好きな虫を通して英語も学べて一石二鳥ですね。
すべてイラストで描かれていますので、虫のリアルな写真が苦手な方にもオススメです。
- 日本の昆虫と世界の昆虫
- 200種以上掲載
- 2歳~小学校低学年向け
- 大きいサイズ
- 全ページ厚紙
- 窓を開けると虫の解説などが隠れており、虫について楽しく学べる
- 英語に親しめる
- イラストのみ
- 「何かわからない虫を調べる」といった使い方はできない
- ひらがなとカタカナのみ
ちょっとマニアック!?もっと専門的な昆虫図鑑
くらべてわかる昆虫
こちらの図鑑は、見分けがむずかしい昆虫を見分けることができるよう、見分け方のポイントが書かれています。
バッタやイナゴは同じに見えるんですが、こちらの図鑑で調べると見分けることができますよ。
また、昆虫素人の私が一番気に入っているところは、昆虫の分類がわからなくても調べることができるところです。
ほとんどの昆虫図鑑は分類別になっています。
しかし、虫の基礎知識がない人にとって、それが結構ネックだったりするんです。
図鑑で虫の名前を調べる時、たとえばそれが蛾か蝶かを見分けた上でページを開かなくてはなりません。
蝶のページを見たけれど載っていない、では蛾のページを開いて探し直す・・・みたいな感じで、図鑑の中を行ったり来たりして、調べるのに時間がかかります。
しかし、こちら図鑑は「白いチョウ・黄色いチョウ」というページに、蝶も蛾も一緒に載っています。
分類がわからなくても、調べたい昆虫の色や形の特徴から調べることができます。
掲載種はそこまで多くないので、メインの昆虫図鑑の補助的な役割で使うのがオススメです。
ふりがなはなく、高学年~大人向けの図鑑ですが、昆虫を特定するときに非常に便利です。
- 約750種掲載
- そっくりな虫、見かける場所などで分類
- 1匹ごとに簡単な解説と、分類・体長・分布・出現期などの情報
- ふりがななし
身近な昆虫識別図鑑
こちらの図鑑も上で紹介した『くらべてわかる昆虫』と同じ、見分けがむずかしい昆虫を見分けることができるよう作られた図鑑です。
同じように見分け方のポイントが書かれていますが、『くらべてわかる昆虫』と大きく違う点が、一般的な図鑑と同じ分類別になっているところです。
先ほどもお話ししましたが、虫について無知に近かった私は、蛾なのか蝶なのか迷いまくっていました。
今でこそ違いがわかるものの、昆虫に接してこなかった私みたいな母親が、分類別になっている図鑑を開くと、特定するまで本当に時間がかかるんですよね。
なので、前で紹介した『くらべてわかる昆虫』の方が『身近な昆虫識別図鑑』より初心者向けかと思います。
こちらの図鑑は生きている虫の写真が使われているのが特徴で、とても参考になります。
こちらもふりがなはなく、高学年~大人向けの図鑑ですが、長く使えると思いますので紹介させていただきました。
- 約1300種掲載
- 分類ごとに掲載
- 1匹ごとに簡単な解説、分布などの情報
- 生きている虫の写真
- 持ちはこびできるサイズ
- ふりがななし
「くらべてわかる昆虫」「身近な昆虫識別図鑑」の比較
どちらの図鑑も、昆虫の見分け方で困った時に使う図鑑です。
2冊を比較しましたので、参考にしてみてくださいね。
- 掲載種:『身近な昆虫識別図鑑』の方が多い
- サイズ:『くらべてわかる昆虫』>『身近な昆虫識別図鑑』
- ふりがな:ともになし(高学年~大人向けの印象)
- 『くらべてわかる昆虫』の方がより初心者向き(分類がわからなくてもOK)
- 『身近な昆虫識別図鑑』は生きている昆虫の写真を豊富に掲載
小学館の図鑑NEO イモムシとケムシ
こちらの図鑑は、蝶や蛾の幼虫であるイモムシとケムシについて調べることができます。
甲虫類(カブトムシなど)は載っていません。
息子が見つけた幼虫を一緒に調べる機会が多々あったんですが、昆虫図鑑は成虫メインなので、幼虫はあまり特定できませんでした。
なので、インターネットで「緑 大きい イモムシ」などと適当に検索していたんですが、図鑑ほど正確な情報を得ることができないため、イモムシやケムシが特定できる図鑑を探していました。
幼虫を調べることができる図鑑は他にもあるのですが、息子が小学館の図鑑NEOのDVDのファンなので、半分DVD目当てでこちらを選びました。
付属のDVDも75分の見応えたっぷりな内容で、息子は数え切れないほど見ています。
イモムシや毛虫は脱皮ごとに色や姿が変わる場合も多く、この図鑑だけで特定できないこともあるのですが(全部の姿が載っているわけではない)、それでもインターネットで検索するよりもずっと楽になりました。
子どもが読むには十分の内容です。
子ども向けのコスパの良い昆虫図鑑を探している方は、こちらの図鑑もオススメです。
- 約1100種の日本のチョウ目の幼虫を掲載
- 分類ごとに掲載
- 1匹ごとに簡単な解説と、分類・体長・分布・幼虫が見られる時期、食べ物などの情報
- 生態写真が豊富
- 75分のDVDつき(ドラえもん登場)
- ふりがなあり
ずかん さなぎ
見開きのページに、さなぎの写真と解説が2~3種類ほど載っており、幼虫や成虫の生態写真も豊富に掲載されています。
正直なところ、わが家ではさなぎを見つけて「これは何のさなぎだろう?」と調べたことがほとんどなく、実用的かと聞かれたら、あまりそうではないのかもしれませんが・・・
マニアックな内容で読み物としておもしろいのと、あまり持っている人がいないのでは?と思ったので、紹介させていただきます。
移動することができないさなぎが、敵に見つかったらおしまいです。
さなぎが敵に見つからないための工夫や、敵から身を守るための工夫を学ぶことができ、とても興味深いです。
さなぎについて知れば知るほど、生命の不思議とおもしろさを感じることができる一冊です。
- 約200種の日本で見られる昆虫のさなぎを掲載
- 分類ごとに掲載
- 1匹ごとに解説、体長、分布、場所、時期などの情報を掲載
- 豊富な生態写真
- ふりがなあり
テントウムシハンドブック
『テントウムシハンドブック』は薄くて小さな持ち運びができるタイプのテントウムシ専門の図鑑です。
こちらの図鑑はかなり専門的ではありますが、非常にわかりやすく、わが家ではトップクラスに出番が多いです。
私はテントウムシの見分け方が全然わかりませんでした。
息子に「これ何テントウ?」と聞かれて、一般的な昆虫図鑑を開いても特定できないことが多かったんです。
テントウムシってすごく種類が多く、同じ種類でも模様が何パターンもあったりするので、特定が本当にむずかしかったんです。
しかし、こちらの図鑑はナミテントウの模様だけでも11パターンも載っていて、素人でもほぼ特定することができます。
実際の大きさも載っており、似ている模様であっても大きさで判別でき、使いやすいです。
テントウムシが好きな小さな子どもがいるご家庭にオススメの図鑑です。



文一総合出版ハンドブックシリーズについては、別の記事でまとめている最中ですので、興味がある方はお待ちください♪
- 115種の日本で見られるテントウムシを掲載
- 小さくて薄いのでコンパクトなかばんにも無理なく入る
- 1匹ごとに解説と、大きさ・分布などの情報を掲載
- ふりがななし
学研の図鑑LIVE POCKET 危険・有毒生物
こちらは、日本に生息している危険・有毒生物についての図鑑です。
魚類や植物などと一緒に昆虫も載っています。
息子が昆虫に興味を持ち始めた2歳のころ、見つけた虫を躊躇なく触ろうとして困っていました。
今まで虫とりをしてこなかった私は、虫についての知識が全くといっていいほどなく、虫を触ろうとする息子にハラハラし、時には強く「ダメだよ」と言ってしまうこともありました。
必要以上にハラハラするのも、子どもに強く注意するのも本当にストレスだったので、危険な昆虫を知っておけば広い心が持てるのでは?と思い、子どもと一緒に勉強する目的で購入しました。
持ち運びできるサイズで、しばらくはこちらの図鑑を持ち歩きながら虫とりをしていました。
子ども向けの図鑑ですので、親子で一緒に学べるところがいいですね。
スマホで映像も見ることができますよ。
おかげさまで、私は危険な昆虫も多少わかるようになりましたし、息子は私以上に危険な虫にくわしくなり、自分で身を守れるようになりました。
昆虫が好きな幼児がいる家庭には、一冊あると大変便利です。
- 約450種の日本に分布している危険・有毒生物を掲載
- 分類ごとにわけて掲載
- 1匹ごとに解説、体長、見られる時期と地域、食べ物などの情報を掲載
- 持ち運びできる小さいサイズ
- スマホで動画が見られる
- ふりがなあり
手すりの虫 観察ガイド
公園などの手すりにいる虫に焦点をあてたユニークな一冊です。
「観察ガイド」というタイトルですが、写真とともに1匹ずつわかりやすく解説されているため、図鑑として紹介させていただきます。
春夏秋冬ごとに手すりで見られる虫(関東)について解説されています。
手すりのような人工物には昆虫が集まってくるそうで、実際に近くの公園の手すりを見てみると、トンボやテントウムシ、カミキリムシがいました。
ふりがながついておらず、高学年~大人向けの本かとは思いますが、写真やイラストが多く、眺めるだけなら小さな子どもでも楽しめます。
わが家は公園に行くことが多く、近くの公園の手すりにいる虫に興味があったため、購入しました。
クモやヤスデなど昆虫意外の虫も多く載っています。
子どもと公園に行く機会が多い方や、身近にいる小さな虫に興味がある方にオススメです。
- 約300種の関東の手すりにいる虫を掲載
- 季節ごとに分けて掲載
- 1匹ごとに解説、虫の生息地域、手すりでの出現時期、出現度などの情報を掲載
- 持ち運びできるサイズ
- ふりがななし
まとめ
今回は、昆虫図鑑のオススメを定番のものからマニアックなものまで幅広く紹介しました。
どの図鑑も親子で一緒に読むことができます。
気になった図鑑はぜひチェックしてみてくださいね。
参考記事
- プレジデントウーマン『「知らない言葉をスマホで調べてはいけない」平成生まれの脳科学者が小中学生1人1端末時代に訴えたいこと』2024/07/16閲覧 ↩︎