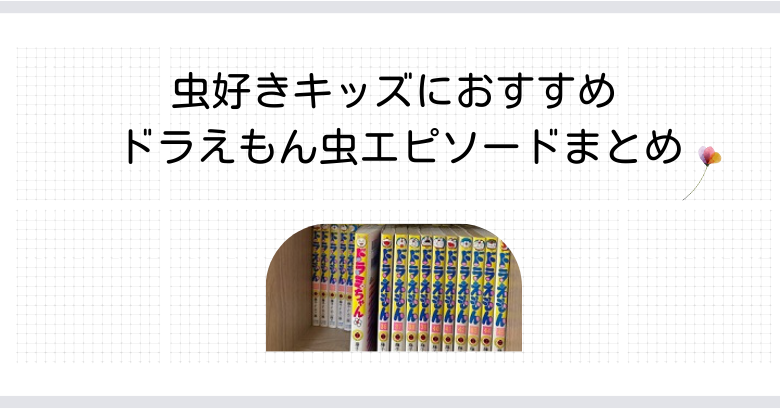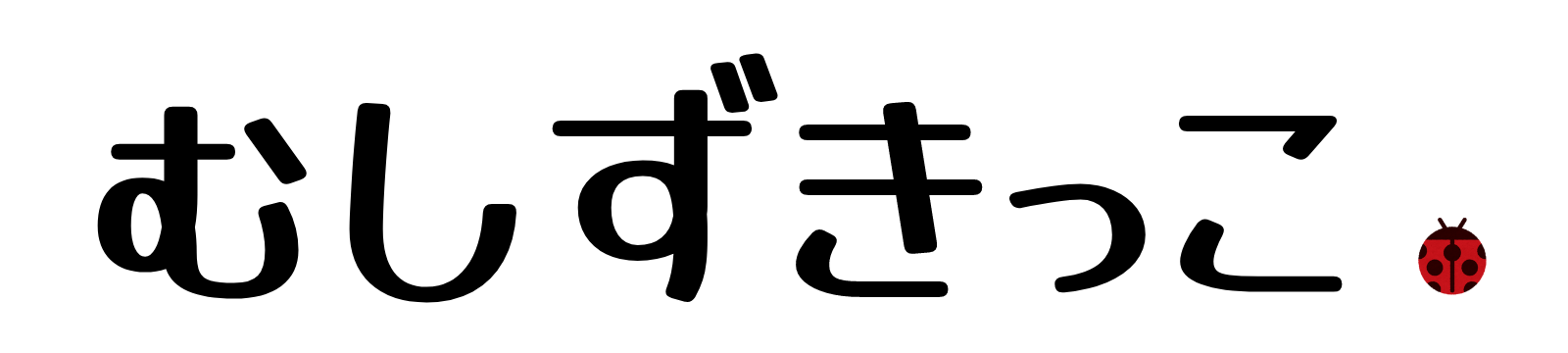みなさんはおりがみ遊びは好きですか?
おりがみ遊びは、誰でも一度はしたことのある日本の伝統的な遊びですね。
小1の息子はおりがみ遊びが大好きです。
そして、母である私自身もおりがみ遊びが大好きで、子どもの頃はよくおりがみを折っていました。
どの世代にとってもおりがみは身近で、特別でも何でもない遊びではありますが、子どもの発達や学びにとてもよい影響があると言われています。
今回は、おりがみ遊びで育つ力、また、オススメのおりがみの本とYouTubeチャンネルについて紹介したいと思います。
- よく遊んでいるおりがみで一体どんな力が育まれているのかを知りたい
- おりがみが苦手だけど、さまざまな効果があることを知ることで挑戦するモチベーションにつなげたい
- 幼児~小学生向けのおりがみの本やYouTubeチャンネルのオススメを知りたい
という方へ向けて、体験談を交えながらお話ししたいと思います。
 むしはは
むしははおりがみが好きな方も、ちょっと苦手だけど挑戦してみたい方も、ぜひ参考にしてみてくださいね。
おりがみ遊びで育つ力


おりがみ遊びは、子どもの発達や学びにたくさんの良い効果があると言われています。
一体どのような効果があり、どのような力が育まれるのでしょうか?
1. 考える力(思考力・集中力)
おりがみは、折る順序や形を考えながら進めるため、
- 注意深く観察する力
- 順序立てて考える力
- 最後までやり遂げる集中力
のような思考力・集中力がつきます。
作品の難易度が上がるほど上記の力が必要になってくるため、苦手な方もいるかもしれませんが、スモールステップで、徐々に難易度をあげていけば、おりがみに対して苦手意識がつかないかと思います。
少しずつレベルアップすれば思考力や集中力も徐々についてきます。



子どもに何か挑戦させるときは、とにかく苦手に思わせないことが大事だったりしますよね。息子もおりがみ遊びを通して思考力や集中力がついたように感じています。
2. 手先の器用さ(巧緻性)
紙を正確に折る、角を合わせるといった動作を繰り返すことで、
- 手指の細かい動きのコントロール
- 目で見て手を動かす力(目と手の協応)
が発達します。
これらは、文字を書く、図形を描く、工作をする、などの力にもつながります。
おりがみを折るときは、目で「どこを折るか」見て、手で「紙をつまんで折る」動きをしますよね。
このように、目の情報と手の動きが連携し、手指を細かく動かして折ります。
そうすると、徐々に手先が器用さが発達していきます。



息子は角と角をピッタリと合わせることが苦手ですが、ズレると作品の仕上がりに影響が出ることを知ってからは、指をうまく使うように頑張っています。本当におりがみは手先の器用さを育むにはピッタリの遊びだと思います。
3. 創造力・想像力
おりがみ遊びは、自分なりの色や折り方を工夫したり、組み合わせたり、完成に向けていろいろと想像することで、創造的な発想が育ちます。
本を見て折るのもいいですが、自分で自由に折ったり切ったりしてみると、また新しい発見があるかもしれません。
自分であれこれ想像しながら作り上げた作品は、世界でたったひとつの作品です。


自分の好きな物をおりがみで自由に表現している時の子どもの表情はとてもいきいきとしています。
おりがみ遊びは、楽しみながら創造力・想像力を育むのにピッタリですね。



違った色味や質感、柄のおりがみをいろいろ準備してあげると、より想像を広げることができるようでした。100均にはいろいろな種類のおりがみが売っているので、親子で一緒に選んでみてはいかがでしょうか。
4. コミュニケーション力
おりがみ遊びは親子や友達とのコミュニケーションにもなります。
「どうやって折るの?」「ここはこうだよ」と教え合う中で、
- 人の話を聞く力
- 説明する力
- 協力する姿勢
が身につき、コミュニケーション力が育まれます。
息子は学校でもおりがみをして遊ぶことがあります。
お友達が折っていて「いいな!」と思った作品は折り方を教えてもらったり、逆に「それ作りたい!」などと話しかけてくれたお友達には教えたりしているようです。
このように、おりがみを通して交流が生まれ、教え合うことでコミュニケーション力が育まれます。



友達から教えてもらって作った作品はいつもうれしそうに持って帰ってきて、「捨てないで!」と言って、大切にしています。
5. 自信・自己肯定感
1枚の紙から形ができあがる経験は、子どもにとって大きな喜びです。
そして、「できた!」という達成感は「おりがみができる」という自信に変わり、「次はもう少し難しいものを折ってみよう」と挑戦する力につながります。
息子の場合、1枚の紙から大好きな虫が何匹もできるので、折り紙遊びを覚えた頃は虫ばかり折っていました。


最初は簡単に折れる「セミ」のような作品を何度も何度も作り、成功体験を積み重ねながら徐々にレベルアップし、最近は「立体カブトムシ」のような難易度の高い作品へ挑戦できるようになりました。
難易度があがる度に、わからなかったりうまくいかない場面も出てきますが、簡単な作品をくり返し作ってきたことで「やってみよう」「失敗してもいい」と思えるように成長していました。
少しずつ難しいおりがみ作品が作れるようになると、親である私たちも「こんなすごいもの作ったの?」とか「かっこいいのができたね」などの言葉が自然と出てくるのではないでしょうか。
- 少しずつ上達して「できた!」が増える→自信が育つ
- 「やればできる自分」を認められる→自己肯定感が上がる
このように、①②をくりかえすおりがみ遊びは、自信と自己肯定感を同時に育てることでできるのです。



自己肯定感があると失敗しても「また挑戦しよう」と思える。
→ その繰り返しが成功体験になり、自信が育つ。
自信と自己肯定感は深く関係し合っていると言えますね。
6. 図形感覚・空間認識力
おりがみ遊びを普段からしている子は、「線対称」「角」「三角・四角」などが身近にあるので、算数で図形問題が出てきたときに、さほど抵抗なく取り組むことができます。
私は塾講師をしていたことがあるんですが、図形問題は計算問題ほど簡単に演習の成果が出ません。
図形問題は図形を正しくとらえる力が必要ですが、これは子ども時代にどれだけ図形と親しんで、図形感覚や空間認識力を育んできたかによって変わってくるのではないかと思っています。
積み木やブロック、野菜を切る料理など図形感覚や空間認識力を育むのにいいと言われているものはいくつかありますが、その中で最も手軽にできるのがおりがみ遊びではないかと思っています。
おりがみは、おもちゃ、箱、袋・・・と、どんな形にも変えることができます。
1枚の紙が変化していく過程で、「線対称」「角」「三角・四角」に出会うことができます。
このように、おりがみ遊びを通じて図形と親しむことは、算数の土台づくりにつながります。
おりがみ遊びで育つ力まとめ
| 育つ力 | 具体的な効果 |
|---|---|
| 思考力・集中力 | 手順を考えながら最後までやり遂げる |
| 巧緻性 | 手先の器用さ・筆記力等の基礎 |
| 創造力・想像力 | 自分で工夫・アレンジする力 |
| コミュニケーション力 | 教え合ったり協力する姿勢 |
| 自信・自己肯定感 | 成功体験の積み重ねによる自信・自己肯定感 |
| 図形感覚・空間認識力 | 算数・空間認識の土台づくり |



以上の6つの力の他に、息子の場合は忍耐力もつきました。作品が難しければ難しいほど、完成までにイライラするようで、おりがみ遊びは気持ちのコントロールの練習にもなっています。
オススメのおりがみの本・YouTubeチャンネル
今まで、息子と一緒に本やYouTubeを見ながら、いろいろなおりがみ作品を作ってきました。
ここからは、わが家でよく使っている本やYouTubeを中心にオススメを紹介したいと思います。
完全版 おりがみ大全集
「この一冊があれば大丈夫」と言ってもいいほどのおりがみ本です。
「つる」や「ふうせん」といった誰でも一度は折ったことがあるおりがみから、生き物、乗り物、植物、遊べるおりがみ、使って楽しめるおりがみ、箱や袋などの実用的な小物、季節や行事に関係するおりがみ・・・と、収録作品数の多さと幅広いジャンルが特徴です。
難易度の高いものはほとんど載っていないので、幼児~小学生にもちょうどよいです。
図鑑くらいの大きさがある本なので、折り図も大きく見やすい上、机に開いても閉じない仕様になっており、折りながら本を見る作業がしやすいです。
定番作品を中心に幅広いジャンルの作品が多数掲載されていて、幼児~小学生向きの見やすいおりがみ本を探している方にオススメです。



家にあるおりがみ本の中で、息子が一番使っている本です。漢字にはすべてふりがながついているので、ひらがなが読めれば1人で読んで折ることができます。大好きな昆虫やぴょんぴょんガエルといった遊べる作品をよく作っています。
決定版やさしいおりがみ
こちらのおりがみ本も定番作品を中心に、つるやかぶとなどの子どもの頃から親しまれている作品、生き物、植物、名札や箱などの実用的な小物が多数掲載されています。
A5くらいのサイズで持ち運びがしやすいため、帰省する時などに便利かと思い購入したおりがみ本です。
折り方の説明はすべてひらがなで書かれているので、ひらがなが読めれば1人でも本を見ながら折ることができます。
「かんたん」「ふつう」「がんばれ」と3段階に分けた難易度マークがついていますので、マークを参考にしながら挑戦することができます。



つるに「普通」、手裏剣に「がんばれ」のマークがついています。掲載されている作品の難易度の目安として参考にしてみてください。
持ち運びしやすいサイズで、幼児~小学生向きの定番作品を中心としたおりがみ本を探している方にオススメです。
大人気!! 親子で遊べる3~5才のたのしい!おりがみ新装版
幼児を対象としたおりがみの本です。
掲載作品は折る回数が少なめのものが多いので、挫折しにくく、「できた!」という成功体験を積みやすいです。
また、おりがみ初心者にもわかりやすい大きな折り図が特徴です。
はじめてのおりがみに挑戦する小さな子向けに、ハードルが低めのおりがみ本を探している方にオススメです。



わが家でも3~5才向けのおりがみ本は使っていましたが、使った期間はとても短かったように思います。年少~年中くらいの小さな子が1人で折れる作品メインの本は少ないので、そういった本を探している方にはオススメですが、コスパで考えるなら幅広い難易度の作品が載っている本がいいかもしれません。
親子でいっしょにつくろう!男の子(女の子)のおりがみ
おりがみの本の中には、男の子向けや女の子向けにそれぞれが作りたくなるような作品を中心に掲載されているおりがみ本もあります
たとえば、わが家が使っている『親子でいっしょにつくろう!男の子のおりがみ』では、恐竜、昆虫、動物、乗り物、紙飛行機などが多数掲載されており、これらのジャンルが好きな男子は「これ作りたい!」と連呼すること間違いなしの内容になっています。
例えば昆虫だと「デラックスかぶとむし」や「ヘラクレスオオカブト」という、よりリアルさを追求した立体の作品が載っていたり、「グライダー紙飛行機」「ブーメラン紙飛行機」といったかっこいい紙飛行機も載っています。



昆虫10種、乗り物14種、恐竜10種、おもちゃ23種、どうぶつ13種、おばけ8種が掲載されています
「かんたん」「ふつう」「むずかしい」「すごくむずかしい」の4段階に分けた難易度マークがついていますので、自分のレベルにあった作品かどうかを判断しやすいです。
本全体の難易度でみると、『完全版 おりがみ大全集』や『決定版やさしいおりがみ』に比べるとむずかしい作品が多く、子どもから「すごくむずかしい」マークの大作を作るようにねだられることも多いです。
なので、1人で静かに遊んでいてほしい目的で購入するのはあまりオススメしませんが、この本のタイトル『親子でいっしょにつくろう!』とあるとおり、おりがみを通して親子でとても楽しいコミュニケーションができる1冊かと思います。
恐竜や昆虫、乗り物が大好きな子、また、親子で一緒におりがみで遊んでみたいという方にオススメの1冊です。
大きさはB5変形判で『決定版やさしいおりがみ』より大きく、『完全版 おりがみ大全集』より小さいサイズ、折り方はすべてひらがなで書かれています。
女の子向けはこちら



アクセサリー・お花・スイーツ・かわいい小物などが載っています。挿し絵も作品もとってもかわいい♡
ばあばのおりがみチャンネル
最後に、息子がよく見ているおりがみのYouTubeチャンネル『ばあばのおりがみチャンネル』を紹介します。
息子は紙飛行機作りが大好きで、紙飛行機の折り方を紹介しているYouTubeを片っ端から見まくっていたんですが、圧倒的にわかりやすいチャンネルがこの『ばあばのおりがみチャンネル』でした。
イカ飛行機や羽ばたく飛行機など、ユニークでよく飛ぶ飛行機の作り方が多数紹介されています。
紙飛行機だけでなく、遊べるおりがみ、クリスマスやお正月などの季節のおりがみ、飾って楽しめるような美しい作品、ポチ袋や箱などの小物など、さまざまなジャンルの作品の折り方を教えてくれます。
とてもわかりやすく、凝った作品もおおいので、子どもから大人まで幅広い世代で楽しめるチャンネルです。



『ばあばのおりがみチャンネル』は教え方が本当に上手でわかりやすいです。複雑な折り方のところは本よりも動画の方がわかりやすいですし、本であまり見たことのないような作品にも出会うことができるので、「本が飽きたな」という方にはYouTubeもオススメです。
まとめ
今回は、おりがみ遊びで育つ力、また、オススメのおりがみの本とYouTubeチャンネルについて紹介しました。
手軽にできるおりがみ遊びですが、その効果はすばらしいものがありますね。
小さな子どもの発達や成長に必要な要素がおりがみ遊びにたくさんつまっています。
大人の認知症予防に効果があるのも納得です。
ぜひ親子で楽しんでみてくださいね。